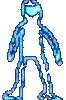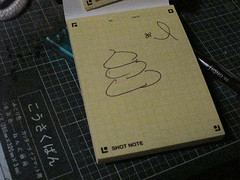ばるぼら (著) 「岡崎京子の研究」アスペクト (2012/7/11)
漫画家の岡崎京子の作品は、有名なものをポツポツと読んできたものの、自分的には印象深く個人的な思い出もあります。20年ぐらい前の話だとは思います。
最初は、何か雑誌のイラストで読み流していたのかもしれません。
その後、高校時代のクラスメイトが学校で読み捨てた雑誌CUTIEから「リバースエッジ」を読み出し、漫画の中で出てくる「梅屋敷のレントゲン藝術研究所にいこうよ?」といった劇中のデートの誘い文句で、なんとなく中原浩大や村上隆という若いアーティストが展示しているギャラリーに行ってみたいと思っていた地方の高校生でした。
大学で上京して、僕自身は全く岡崎京子さん個人とは交流がありませんでしたが、渋谷にあったギャラリーP-HOUSEのイベントなどで何度か本人を見かけたり、大学の頃の友人(「チワワちゃん」のクマちゃん?)が少しだけ岡崎京子のアシスタントをしていたようでその様子など聞いてはいました。
最初は、ひと言コメントが面白く「ばるぼらアンテナ」というサイトを、僕はネット巡回していました。
その後、「betweens!」というミニコミを求めてコミケに行ったとき、初めてばるぼらさんを見かけました。ある世代ある世界での名著!奇書!といわれる「教科書には載らないニッポンのインターネットの歴史教科書」や、美術圏外からの美術批評本「モダニズムのナードコア」や、僕もどこかで参加している大変特殊なネットレーベル「赤身レコーズ」など、大変興味深い著作をされていて調査力、記録力、編集力は大変尊敬しており。
「教科書には載らないニッポンのインターネットの歴史教科書」を初めて読んだとき、僕も僕なりに教科書にのらない自分による美術史を考えていって良いはずだと思う切っ掛けになり、自分なりに情報を編集記録していたことがありました。いや、その情報を目にしなかったら、そのようなことは考えもしませんでした。
多分、三度ほどお見かけしているはずですが、文章の印象が強くお姿はすぐ忘れて思い出せません、そういうところに流石ネットワーカーと感じています。
そのほか、高円寺の円盤にて、ばるぼらさんの5時間おしゃべりし続けるイベントにも行きました。小室哲哉の話や、imoutoidという人について名前を僕は初めて聞きましたが、会場風景として印象的だったのは、ばるぼらさんがお話しすることを丁寧に聞き取ってメモする赤田祐一さんの風景でした。なんとなく想像だけであった、ばるぼらさんと赤田祐一さんが情報を読みあってる姿を生で見ると、何かの編集文化のミームが続いていくような風景に見えて感激しました。 そんな、ばるぼらさんによる岡崎京子の本。岡崎京子の情報として音楽雑誌に掲載された読者投稿のイラストから活動は始まり、その前史のこと、80年代の自販機エロ本での連載活動や、様々なジャンルの出版物に掲載された岡崎京子のイラストを網羅。そして名著、「リバースエッジ」や「PINK」、「へルタースケルター」へと活動の展開とその同時期の活動、交通事故と事故後の情報もある程度載っています。
近日公開映画「ヘルタースケルター」に向けた、岡崎京子をしらない人には知る機会になるガイドであり、「東京ガールズブラボー」を読んでる方には、そのバックグラウンドも見えてくる。さらに、80年代から90年代、様々な方面や媒体で活動された岡崎京子だけに、克明な情報で書かれたこの本を読み込んでいくことで、何かハッキリとした80年代から90年代が見えてくる本に仕上がっています。
本書の中で知った、岡崎京子のコメントとして印象的だったのは
「だって世の中がマンガに追いついちゃったでしょ。つらくて悲しい話はそろそろやめて、そういうこともわかったうえで幸せな話を描こうかと。マンガっていつも少し先の虚構を描かないとね」(P.186)
というコメントでした。
この本の出版の経緯を出版の方から伺ったところ、色々な事情があり研究者の本として、岡崎京子の大きな画像は使えなかったそうです。しかし、本の帯にある画像が、岡崎京子の画像を全く使っていないのに岡崎京子の本に見えてしまう!驚くことに、2002年の「ヘルタースケルター」の表紙が、2012年の「岡崎京子の研究」の表紙からパクられていました。(アマゾンなどインターネットの本屋さんでは、帯の画像は掲載出来ないルールだそうです。是非、本屋さんで買って確かめよう!)
この本の表紙が出来たり、AKB48の秋元才加がgoogle+で「女子! 岡崎京子は 絶対読みましょう?バイブル?」と申すところや、映画で沢尻エリカがリリコを演じるところで、1996年の岡崎京子が2012年に追いついたのでしょう。いや、岡崎京子のファンが作り出す世界が、岡崎京子の虚構なのでしょう。
本が出来るにあたり驚いた話。本の表紙裏には、”copyright: David Lynch”と、小さく書かれており、実際にデビッド・リンチが承諾して作品の使用許可を頂いたようです。デビッド・リンチが岡崎京子の漫画を認識しているということと、著者と編集者の工夫と行動力にも驚きました。一本の日本映画が公開される時期に、併せて出版されるこの本が、世界的な映画監督の作品に表紙を飾られてる、なんて不思議なことなんだろう!逆に 「岡崎京子の研究」という本があって、岡崎京子の漫画や映画が出来たように感じなくもないとも思えました。
ばるぼらさんのこの本を読むことで、岡崎京子を介して80年代90年代の世界が見えてきて、そこから立ち上がる岡崎京子の作品像から2012年が見えてくるように感じました。
また、この本を通して岡崎京子とばるぼらさんの活動や成果を思い出しながら、今この記事を書いている時、自分の過ごしてきた何かの時間の流れを追体験しているような気分にもなりました。
「岡崎京子の研究」は、著者の編集の性格上、80~90年代あたりのある期間ある世界の話題が凄い密度で書かれている。しかし、歴史って観点で見ると、10年間、20年間、東京の出来事でというと、短い時間、狭い場所の単位ともとれなくもありません。
個人的には、なんとなく岡崎京子を読んだ時期、なんとなくニーチェや、バタイユとか、自分なりの理解でそれなりに読んでいた頃で、自分なりに何となく関連性を結ぶように感じて読むようなところもあったとは思う。その体験を思い出して今思うのは、1980年代とか90年代の時代から離れた時代、東京から遠い場所にあるものと、テーマ設定で関連づけて読書体験をしたいなと思いました。
僕個人としては、岡崎京子は好きであるものの、ばるぼらさんも含めて、自分よりもっと明晰で、お好きな方は想像できたし、自分が岡崎京子について語るべきことはあまりないとは思っています。
しかし、物心ついた頃からサブカルに興味をもち、例えば、クラブミュージックや、漫画や、現代アートなど好きだった身では、どうもサブカルが大好きなぶん、自分の何処かに、サブカル界コンプレックスが重くのしかかるように思うときもあり、偶々偶然であれ、ばるぼらさんの岡崎京子の本に関われて、自分の中のサブカル界コンプレックスが成仏したような気分にもなりました。
また、岡崎京子というと、全く知らない、名前を聞いたことある、”オッサン・ホイホイ”と思ってしまう未読の若い方もいるとはいます。そういうかたも、この本の出版や映画の公開を切っ掛けに、岡崎京子の本にふれてみるのは如何でしょうか?多分、今、世の中にある岡崎京子にまつわる本では、日本一!宇宙一!詳しく!面白く!キモい!本 (^o^) です。興味がわいた方は、この 「岡崎京子の研究」並びに、岡崎京子の漫画を読んでみるのは如何でしょうか?僕も、細かいモノはあまり読んでいないで、この機会に少し探して読んでみようとは思いました。